
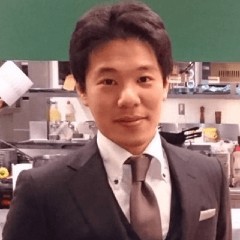
不動産投資をはじめる際に気になるのが所得税などの申告・納税手続きへの影響です。給与収入を主な収入源としている場合は、会社が年末調整を行ってくれるため、自分で確定申告を行ったことがない方もいるでしょう。しかし不動産投資をはじめる場合は、収入額によっては確定申告が必要となる場合があります。
本稿では、不動産投資をはじめても年末調整で申告・納税を完了させる方法や所得税などの税額計算・確定申告手順・注意点について解説していきます。
目次
年末調整と確定申告の違い
所得税は、原則として国内で得られた1年間の所得をもとに自身で税額を計算し、定められた期日までに納税する「確定申告」を行うことが必要です。しかし税額の申告・納税には、一定の条件を満たした場合にのみ選択できる「年末調整」という制度もあります。正しい納税は、投資活動を継続するうえでも重要な要素の一つとなるため、年末調整と確定申告についてしっかりと把握しておきましょう。
年末調整適用の条件とは?
所得税は、原則として自分で申告や納税を行うことが必要です。しかし給与収入を主な収入源としている場合は、勤務先の企業が社員に代わって所得税の税額を計算し納税を行う「年末調整」を利用していることが多いでしょう。年末調整の納税期限は、翌年1月10日となるため、勤務先によって11~12月の年末に実施されることが多い傾向です。
年末調整は、納税関係の手続き負担を軽減する優れた制度ですが、適用するには以下に示す諸条件をすべて満たす必要があります。
【年末調整の適用条件】
- ビジネスパーソンや公務員などの給与所得者(パート・アルバイトなど勤務形態は問わない)
- 給与および退職金以外の所得が年間20万円以下
- ダブルワークなど2ヵ所以上で就労し複数の源泉徴収を行っていない
- 災害に被災するなどして所得税などの徴収猶予や還付を受けていない
- 年間の給与収入が2,000万円以下
確定申告が必要になる場合は?
年末調整の適用条件から不動産投資をはじめて所得が20万円を超えた場合は、年末調整が適用できなくなります。そのため、自身の所得と税額を申告して納税する「確定申告」を行うことが必要です。一見すると納税関係の手続き負担が増えるため、デメリットを感じるかもしれません。しかし年末調整は、いわば確定申告の簡易版です。
そのため災害や盗難による被害を受けた場合に減税となる「雑損控除」や一定額を超える医療費を負担した場合に適用される「医療費控除」といったセンシティブな所得控除を適用することができなくなっています。また損失の通算による税還付も受けることができません。そのため以下のようなケースでは、確定申告のほうが正確な納税を行うことができます。
・不動産所得が損失となっている
・年末調整では適用できない所得控除を利用する
・不動産所得が損失となるケース
不動産所得は賃料収入などの収益から不動産投資に関わる諸経費などの支出を差し引いて算出しますが、この際、支出のほうが大きいと不動産所得が損失となり、給与所得や事業所得などと損益通算を行うことになります。
不動産所得が損失となるケースとして、以下のような場合が考えられます。
賃借人の退去による空室の発生で賃料収入が減少した場合
建物や設備などを交換・修繕したための諸経費の上昇や、満室経営であっても減価償却の実施により不動産所得が損失となる場合
また、賃借人が賃料を滞納している場合は実際には賃料収入が得られていませんが、未収地代家賃として不動産収入に計上する必要があり、所得税・住民税の負担も生じます。
しかし、未収地代家賃が現実的に回収不可能と確定した段階で損失が確定し、貸倒損失として不動産所得算出に損金処理することが可能となります。
未収地代家賃が賃借人の収入からみて過大であり、回収の見込みがない場合は債権放棄することで不動産所得を圧縮または損失とし、税負担の還付を受けることができます。
・年末調整では適用できない所得控除を利用するケース
年末調整では適用できない所得控除には、以下の3つがあります。
寄附金控除
雑損控除
医療費控除
寄付金控除は特定の団体や自治体などに対して行った寄付が対象となります。近年注目されているふるさと納税も寄付金控除に該当するため、ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請していない場合は確定申告を行う必要があります。
雑損控除は災害や盗難などによって被害を受けた場合に、その被害額や被害を回復するために支払った修繕費などを確定申告を行うことで控除することができます。しかし、詐欺や恐喝による被害は雑損控除の対象外となっていますので覚えておきましょう。
医療費控除は納税者本人と生計を同じくしている家族が1年間に支払った医療費や医薬品の購入額が一定額を超えた場合、その超えた分を控除することができます。医療費控除には市販されている対象の医薬品を一定額以上購入した場合に利用できるセルフメディケーション税制の2つがあり、確定申告を行うことでどちらか一方を適用することができます。
不動産投資をするサラリーマンが年末調整で提出する申告書類の種類
サラリーマンなどで給与所得が主な方は、確定申告ではなく勤務先を通して行われる年末調整によって税金関係を完了させることができます。
不動産投資をはじめた場合でも年末調整の基本的な流れに変わりはありませんが、収入が増えるため基礎控除や配偶者控除の額に変化が生じる可能性があります。年末調整の申告書類と控除の内容について確認しておきましょう。
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
障がい者や学生・ひとり親など確定申告を行う給与所得者が扶養している家族などに関する申告を行うことで扶養控除の額が算出され適用を受けることができます。
しかし、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書では扶養控除の対象とならない「16歳未満の子ども」に関する情報も記載する欄があります。これは所得控除には関係しないのですが、住民税の非課税判定に関わっています。
個人の所得税は所得が多いほど税率が高くなる累進課税を採用しているため、原則として所得控除は収入の多い方が申告したほうが節税効果が大きくなりますが、16歳未満の子どもに関する申告は収入が少ない方が申告を行うことで住民税が非課税になる可能性があります。
②給与所得者の保険料控除申告書
年末調整では生命保険・介護保険・個人年金保険の保険料の一部を所得控除とする生命保険料控除と、地震保険料の保険料の一部を控除する地震保険料控除を申請することができます。
生命保険料控除は個別の控除枠を持っており控除額の上限は各4万円ずつで、生命保険・介護保険・個人年金保険の合計で最大12万円の生命保険料控除を受けることができます。
地震保険料控除は最大5万円まで控除を受けることができます。投資用物件などマイホーム以外の建物の地震保険料も合算することができるため、不動産投資をはじめた際は申告漏れに注意しましょう。
③給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
基礎控除と配偶者控除・配偶者特別控除は給与所得者の所得によって控除の有無や控除額が変化する仕組みです。給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書は、給与所得者と配偶者の全ての収入額を記載して控除内容を算出します。
ここで記入する収入は不動産投資の収入も含みます。不動産投資を行っている場合は年末調整までに不動産投資による収入と諸経費をまとめておかないと年末調整で申告を行うことができなくなってしまいます。
・記入時の注意点
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の16歳未満の子どもに関する申告は、通常の所得控除とは取り扱いが異なるうえ、夫婦どちらか一方しか行うことができません。共働きの場合は夫婦それぞれの年末調整で2重に申告してしまわないよう注意しましょう。
次に給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書で注意したいのが不動産を売却した場合です。
不動産の譲渡益により所得が増加し、所得合計が1,000万円を超えた場合は配偶者控除が所得要件により適用外となり税負担が大きくなってしまう恐れがあります。
④住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書
一定の要件を満たす住宅を住宅ローンを利用して取得した場合、その住宅ローンの年末残高に対し住宅ローン控除の適用を受けることができます。
住宅ローン控除は初回の確定申告が必要となりますが、2回目以降は年末調整で申告可能になります。この際は勤務先に住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書と住宅ローンを契約している金融機関などが発行する住宅ローンの年末残高等証明書を勤務先に提出する必要があります。
賃貸併用住宅でも住宅ローン控除の適用を受けることができますが、床面積の2分の1以上を自己居住として利用していないと住宅ローン控除を受けることはできません。
また2分の1未満であっても自己居住と賃貸用の床面積で按分するため住宅ローン控除の節税効果は減少してしまいます。
不動産投資の収入と経費
基本的に収入を得るために生じた経費は、収入から差し引くことができます。収入から経費を差し引いたものが「所得」です。所得税は、所得から社会保険控除や扶養控除などを差し引いた金額に対して課税されます。不動産投資における主な必要経費は、以下の通りです。
【不動産投資における経費の例】
- 固定資産税による「公租公課」
- 火災保険などの「損害保険料」
- 設備や建物の修理による「修繕費」
- 新聞代や不動産投資に関する勉強に要した「図書新聞費」
- 不動産会社などとの打ち合わせに要した「接待交際費」
- 不動産会社との打ち合わせなどに使用した電話代やインターネット代などの「通信費」
- 不動産投資のための移動に要した「旅費・交通費」や「自動車関連支出」
- 客付けのために要した「広告宣伝費」や「仲介手数料」
- アパートローンの金利に関わる「支払利息」
- 建物や高額設備の取得に要した「減価償却費」
このように不動産投資における経費は、幅広い分野で計上することが可能です。しかし高額な設備・什器や建物の取得費用は、一度にすべての費用を経費とすることができません。減価償却により一定期間にわたって分割して費用計上していくことになります。減価償却費は、建物の代金などすでに費用の支払いが終わっているため、翌期以降は実際に現金の支出を伴わない特殊な経費です。
そのため不動産投資で収入が手元に残った状態でも減価償却費を計上することで損失となれば所得税の節税効果を得ることができます。
所得税の計算方法と申告の注意点
不動産所得は、所得税の総合課税に区分されるものです。給与や事業収入を源泉とする「給与所得」や「事業所得」などと損益通算を行い算出された所得金額から雑損控除や医療費控除などの所得控除を差し引いて課税所得を算出。課税所得に一定の税率を掛けて所得税の納税額を算出します。例えば以下のケースで確認してみましょう。
| 年収(給与による収入) | 600万円 |
|---|---|
| 給与所得控除 | 164万円 |
| 不動産収入 | 120万円 |
| 不動産経費 | 80万円 |
| 社会保険料控除 | 100万円 |
| 基礎控除 | 48万円 |
所得税の納税額は、以下の計算によって算出されます。
[(給与収入600万円-給与所得控除164万円)+(不動産収入120万円-不動産経費80万円)]-社会保険料控除100万円-基礎控除48万円=課税所得328万円
(課税所得328万円×所得税率10%)-控除額9万7,500円=所得税額23万500円
所得税は、課税所得が多いほど税率が高くなる累進課税制度を採用しています。そのため不動産所得で損失が生じた場合、課税所得が高い人ほど節税効果が高くなる傾向です。しかし節税のために無理に経費を計上しすぎてしまうと資金繰りの悪化を招いてしまう恐れがあります。また通信費や自動車関連支出などを自家用としても使用している場合は、費用の全額を計上するわけにはいきません。
この場合、不動産投資に使用した分のみを計上する「家事按分」を行うことも必要です。このほか不動産所得が損失となった場合は、アパートローンのうち土地の取得費用に関する支払利息は計上することができなくなる点にも注意しましょう。
不動産所得が20万円以下ならば年末調整が利用可能だが、赤字の場合などは確定申告が有利
給与所得者のうちすでに年末調整の適用を受けている方が不動産投資をはじめた場合、所得が20万円以下であれば年末調整で完了させることができます。しかし不動産所得が20万円を超えて年末調整の適用条件を満たせなくなった場合は、自身で確定申告を行い、所得税を納付することが必要です。年末調整では、税還付や雑損・医療費控除などが利用できません。
そのためこうした場合は、確定申告を行ったほうが税負担を軽減できる可能性があります。特に不動産投資の損益は、給与所得などと損益通算できるため、不動産投資が損失となった場合は所得税を算出する元になる課税所得を減らすことが可能です。不動産投資による損失は、主に必要経費が増えたときに引き起こされます。
しかし建物や設備の取得費となる減価償却費は、一度支払ってしまえば翌期以降は現金支出を伴わないため、手元にお金を残しつつ所得税の節税効果も得ることが期待できるでしょう。年末調整と比べると確定申告は手続きが多くなりますが、所得の実態に則した申告・納税を行うことで税負担が軽減される場合があります。
年末調整にこだわらず状況に応じて確定申告でも対応できるようにしておくことがおすすめです。
年末調整に関するよくある質問
Q.年末調整が適用される条件は?
年末調整の適用を受けるには、以下3つの条件を満たす必要があります。
- 給与収入が2,000万円以下であること
- 退職所得と給与所得以外の所得が20万円以下であること
- 副業などで2ヵ所以上の勤務先から給与を受け取っている場合は全ての事業所で源泉徴収と年末調整が行われていること
Q.年末調整ではなく確定申告が必要なケースは?
以下の場合では確定申告が必要です。
- 年末調整の適用要件を満たせない場合
- 住宅ローン減税の初回適用を受ける場合
また、必要ではありませんが、確定申告を行った方が良いケースとして、以下があります。
- 地震や台風などの災害によって被害を受け、その被害から回復するために災害関連支出を行った場合
- 盗難などの犯罪被害による損失の控除を受ける雑損控除の適用を受ける場合
- 傷病などにより多額の医療費を支払ったりセルフメディケーション税制対象の医薬品を一定額以上購入していたりする場合
- ふるさと納税ワンストップ制度を利用していない場合
上記は確定申告を行うことで正確な納税を行うことができます。
Q.年末調整で申告する書類の種類は?
年末調整の基本的な申告書類は、以下の3種類です。
「給与所得者の保険料控除申告書」
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」
さらに住宅ローンを利用している場合は「住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書」と金融機関などが発行する住宅ローンの年末残高等証明書と生命・地震の保険料控除を受ける場合は保険会社が発行する保険料控除証明書をそれぞれ添えて勤務先に提出する必要があります。
>>【無料小冊子】税を理解して賢い投資家になろう - 税金一覧と節税方法を解説
【あなたにオススメ】
・面倒な確定申告の手間を削減するには?
・サラリーマン大家の不動産所得の確定申告
・不動産投資の借入金と金利、確定申告で必要経費になる?
・確定申告で間違えやすい「不動産ローンの必要経費」
・【特集#01】不動産投資初心者が知っておきたい確定申告の基本













