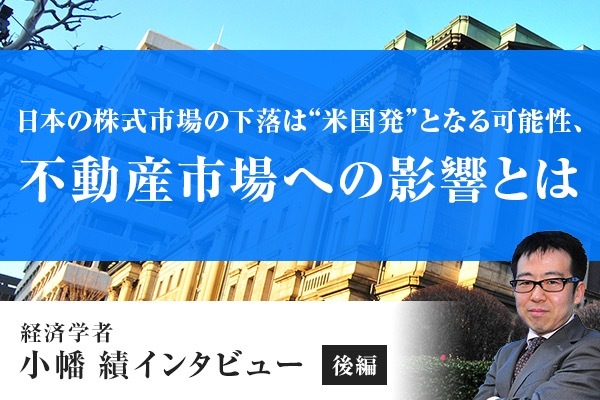
コロナ禍のなか、米国株は史上最高値の更新を続けてきました。日本株も、今年9月6日にTOPIX(東証株価指数)が90年代後半のバブル期以来の高値を更新するなど、上昇傾向にあります。ここでは、前編に引き続き慶応義塾大学大学院准教授の小幡績さんに、日本の株式相場や不動産市場の動向などについてお話をうかがっていきます。
日本の株式相場の下落は“米国発”となる可能性
――日本の株式相場についてうかがっていきたいと思います。9月上旬にTOPIXがバブル期以来の高値を更新しましたが、今後も日本の株式相場は上昇を続けそうでしょうか。
日本の株式相場は、日本独自の事情だけで動いているというより、米国の経済や相場に依存するところが大きくなっています。米国相場はなかなかバブルが弾けないためにここまで膨らんできたわけですが、いつバブルが崩壊してもおかしくない状況です。
中国の不動産大手である恒大集団の破綻リスクが急浮上したことで、9月20日から3営業日ほど日米欧の株式相場は急落しました。この恒大の信用不安がリーマンショックのような世界的な金融システムを引き起こすとの話も見かけますが、私はこの恒大の問題が米国のバブル崩壊に直結するかというと、そうは思いません。
――確かに、世界の株式相場は3日ほど下げましたが、その後は急反発しました。
その急反発が、実はバブル崩壊の兆しなんです。世界の投資家は、恒大のニュースが浮上した直後、それがどの程度ネガティブなものなのか、周囲の顔色をうかがいながら売っていた感があります。とりあえず売ったものの、22日には米国のFOMC(連邦公開市場委員会)の声明を控えていたことがあって、その声明の内容を見極めるために、21日の株式相場は小動きで終わりました。
FOMCの声明は、テーパリング(金融緩和の縮小)の開始時期がほぼ11月に決まったことを示唆する内容でした。さらに、利上げに転じる時期についても、従来の2023年から2022年中に前倒しを見込むFOMCメンバーが増えるなど、いわゆる“タカ派”の色が濃かったわけです。ところが、それでも株式相場は急反発しました。これが何を意味するかわかりますか?
――利上げ時期が前倒しされるというのは、株式相場にとってマイナス材料だと思いますが・・・。
そうです。FOMCの声明は株価下落につながる内容だったにもかかわらず上昇したのは、世界の投資家が「受け入れたくない事実を無視」したから。つまり、いつ暴落が起きるかビクビクしている状態なので、それを示唆する事実からは意図的に目を背けている、ということです。これがバブル相場の末期が近いと考えられる理由のひとつです。もうひとつは、世界の投資家が株を売りたがっている状況であるということ。ここまで相場が長期にわたって上がり続けてきたため、投資家は周囲の顔色をうかがいつつ、売るタイミングを模索しています。これも、バブル相場の後半によく見られる現象です。
今回のバブルではリーマンショックの時とは違って金融機関の懐は痛んでいません。その分のしわ寄せが巨額の財政出動や金融緩和に踏み切った政府と中央銀行に来るでしょう。それによって、リーマンショック以上のバブル崩壊が米国相場に訪れるかもしれません。そうなれば当然、日本の株式相場は大ダメージを受けるでしょう。
――日本の株式相場は“米国発”の要因で崩れるということでしょうか。
基本的にはそうだと思います。日本独自の理由で相場が崩れるとすれば、日本の財政危機に対する懸念がついに市場の材料となるか、あるいは日銀の政策変更に起因するものでしょう。黒田総裁の任期は2023年4月8日まで。任期の終わりが近付く2022年の終盤に黒田総裁が何かをやらかすかもしれません。また、総裁の交代時に何らかの危機が訪れる可能性はあります。
ただ、日本の相場が今年または来年に大きく崩れるとするなら、やはり米国相場の急落が発端になる可能性の方が高いと思います。日本要因は再来年以降になると急速に現実味を帯びると思いますが、米国発のほうが先に起きるでしょう。それまで、相場は急上昇が続くというより、高値圏での推移が続くことになるのではないでしょうか。
不動産市場は、都市部で大きな値崩れはない?
――日本の不動産市場については、どうお考えでしょうか。コロナショック当初は、リモートワークの普及によってオフィス市場に変革が訪れるとの見方が強かったと思います。一部でオフィス空室率の上昇などが見られますが、都市部ではオフィス賃料などに大きな値崩れは見られていません。
まず、勘違いしている人が多いようですが「コロナショックによって変革が訪れる」という考え方は誤りです。コロナショックの以前から動いていた変化が加速しているだけであって、コロナショックそのものが変化を起こしたわけではありません。
確かに、ホテルや観光業界は一時的に大きなダメージを受けています。観光は長期的には回復するかもしれませんが、ビジネス出張は今後も大きく戻ることはないでしょう。リモート会議の普及で大規模ビルのワンフロアを丸ごと借り切るようなニーズは減ると思います。とはいえ、郊外への移転はあまり進まないと思いますね。結局、多くの人がいまだに都心志向なので。郊外好きな人はいるでしょうけど、それが主流になるとは思えません。大規模なオフィスビルのニーズは減ることは確実ですし、長期的にも賃料は少しずつ下落していくと思いますが、暴落はしないと思います。また賃料は確実に下がり、空室率も上がると思いますが、金利などの状況により、不動産の価格自体は、都心部では下がりにくいと思います。株価が暴落したときはまた別ですが。
――郊外の注文住宅の販売は好調のようですね。
個人向けの住宅については、コロナショックを利用したマーケティングが成功している面もあります。一戸建てだと父親が「書斎」を持てるので、リモートワーク向きということもあるでしょう。「お父さんの書斎」がひとつのキーワードになっているのだと思います。あとは、玄関に入った直後、あちこちベタベタ触らなくても手が洗えるとか。本質的な不動産価値とは無縁のところで買う人たちがいるので、ある程度は売れるのでしょう。サラリーマンは自分たちが買える値段でしか買いませんが、現在は低金利下で住宅ローンが組みやすいので、そうした郊外の物件が人気なんだと思います。
もうひとつ、日本の不動産市場が下がらない理由として、世界的にみて日本の不動産が極端に割安ということもあるでしょう。現在の不動産バブルは、株式相場と同時に崩壊することになると見ていますが、それまでは価格の割安さを背景に外国人が買ってくると思います。もっとも、実際にバブルが崩壊すれば誰も買わなくなるので、アジアの富裕層を中心とした投資が行われている物件、投資用のワンルームマンションなどはかなりの値崩れを起こすでしょうし、ハイエンド物件も海外投資家が引けば、これまで急騰した分急落するでしょう。
――コロナ以前はインバウンド需要が不動産市場を押し上げていました。
インバウンドに関しては、今後もさほど戻らないと考えています。コロナ前のインバウンドバブルで、たとえば中国人の「一度は行ってみたい」というニーズは大分こなしたと思います。そのニーズが一巡すれば、今度はリピーターになるわけですが、リピーターとなると特定の観光地に殺到することはなくなるでしょう。不動産価格もそれを反映して、インバウンドにより急騰した物件、地域は下落が続くでしょう。
今後はサービスの内容や質にニーズが移っていくので、インバウンドを狙って建てられた不動産に再び人が集中することはないでしょうね。一方で、昔ながらのいい旅館のように、日本ならではのサービスや価値観を提供できるところは客足が戻ってくると思います。
SPACブームはバブル末期のサイン?
――現在、SPAC(スパック、特別買収目的会社。自身では事業を行わず、事業の買収だけを目的に作られた会社)がメディアでも盛んに取り上げられるなど話題になっています。これについて、お考えをお聞かせください。
米国ではSPACの上場が急増していますが、まずSEC(米国の証券取引委員会)がSPACの上場を認めているのは驚くべき現象ですね。ガバナンスに厳しいSECが普通なら認める訳がない。バブルが政策にも影響を与えている一例ですね。日本でも上場が取りざたされていますが、実体がない企業の上場に対して、元々形式主義の東証が認めるとは思えません。日本でSPACの上場ブームが来るかというと、現状では厳しいでしょう。
ただ、実質的には、上場審査をかいくぐる為の抜け道手段は日本にも存在します。株式相場が暴落している時などに、時価総額が低く、経営難に陥っている上場企業を投資会社が買収して支配下に置くケースなどがそうです。一方、バブル期には、世界的には、SPACのような上場スキームは、いたるところで見られてきました。バブル下では、バブルが崩壊する前にどれだけたくさんのカネを集めるかが勝負。そのため、ガバナンスをすっ飛ばしたファンドスキームが発達するんです。
――バブル下における余剰資金が、そのような動きを作り出すわけですね。
SPACのような仕組みがブームになることも、バブル期の特徴のひとつと言えます。ポイントは、そうした動きがバブルでも末期の時に出やすいということ。ベンチャーキャピタルなどが投じた資金のエグジット(回収)を求める動きが強まることもあって、SPACのような受け皿ができやすいんです。現在のSPACブームも、やはりバブル相場の崩壊が近付いている証拠でしょう。
規制緩和による成長戦略では「真の経済成長」は訪れない
――経済が急回復している米国はともかく、日本では「上がり続けている株式相場と実体経済が大きく乖離(かいり)しているとの声がよく聞かれます。
それは当然ですよ。日本の人々はコロナの影におびえ、不安を抱き、消費行動を抑制してきました。政策というより、個々人が怯えているからで、そんな社会に、カネをばら撒いても、何もおきません。カネがないから消費しないのではなく、行動できないから消費機会がないだけです。コロナという不安は払しょくされない限り、消費は回復しません。
その一方で、市場には巨額の財政出動と金融緩和によってカネがあふれることになります。そのあふれたカネが株や不動産をはじめとしたリスク資産に向かい、相場は上がります。こうして、「コロナショックバブル」が形成されてきました。先ほども触れましたが、今回のコロナショックでは、世界の政府や中央銀行がリーマンショック時を上回る規模の財政出動や金融緩和に踏み切り、それがコロナショックバブルを生み出しました。将来、必ずそのしわ寄せが政府や中央銀行にやってきます。財政破綻は現実のものと捉えておくべきです。
――「今回のコロナショックを契機に規制緩和が進み、イノベーションによる経済成長が起こる」という考え方についてどう思われますか。
ありえません。そもそも、GDPが増加することが経済成長という捉え方が一般的ですが、これが間違っています。GDPの短期的な変動は景気変動であり、構造的な経済成長ではありません。それにもかかわらず、単に数字上のGDPを短期的にかさ上げしようとして、政府に景気対策を求め続けており、この結果、景気対策によって景気が過熱し、それが冷え込み始めると再び景気対策に打って出なければなりません。景気対策をすると、むしろ長期の経済構造の進化への投資は減少しますから、経済成長にはマイナスの影響が生じます。
イノベーションによる経済成長とは、イノベーションが従来の産業構造を壊し、大企業が持つ既得権益の構造が崩れることによって、新しい企業のマーケット参入を促し、新しい価値がもたらされることで起きるものです。現在は、GAFAをはじめとしたごく一部のITの巨人たちによって、新しい独占的な構造、既得権益が作り上げられているだけ。つまり、現代のイノベーションとは、破壊による創造ではなく、単なる企業同士の覇権争いです。覇権による独占者利益を誰が得るかが変わるだけですから、経済の独占構造は変わらず、長期的な経済成長は起きません。
――それでは、「真の意味での経済成長」とはなんでしょうか。
経済成長とはGDPという数字を追い求めるものではなく、人々の生活や社会が豊かになることだと考えています。企業が自助努力でコスト削減を行い、商品やサービスの価格を下げることで、消費者は確実に幸せになれます。また、商品やサービスの質を高めることで、社会が豊かになることも同じです。これらは数字上の経済成長はもたらしませんが、真の経済成長であると私は思います。

>>【無料小冊子】不動産投資ローンマニュアル - 仕組みから審査攻略法までを解説
>>【無料小冊子】40の金融機関と接する融資のプロがコロナ禍でも融資を引き出せる方法を解説
【あなたにオススメ】
・アメリカでは15万円!? 日本では無料が当たり前、世界の救急車事情
・憧れのホテル暮らし。ハイクラスホテルに1年間住んだ場合の費用を徹底比較
・アマゾンの新人賞与3000ドルに既存社員が怒り
・富裕層が通う高級回転寿司でお腹いっぱい食べるとお会計はいくらになるの?














